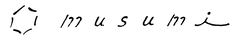【初心者必見】グルテンフリー用語を徹底解説!知っておきたい関連用語集
はじめに:グルテンフリーとは?

近年、健康志向の高まりとともに「グルテンフリー」という言葉を耳にする機会が増えました。
グルテンフリーとは、食事からグルテンという特定のタンパク質を取り除くライフスタイルのことです。
まずは、基本となる用語から見ていきましょう。
グルテン
グルテンは、小麦、大麦、ライ麦などの穀物に含まれるタンパク質の一種です。
パンのふっくらとした食感や、うどんのコシは、このグルテンの働きによるものです。しかし、このグルテンが体質に合わない人もいます。
グルテンフリー
グルテンフリーとは、グルテンを含む食品を摂取しない食事法や、そうした食品そのものを指します。
もともとはセリアック病などの自己免疫疾患の食事療法でしたが、現在では体調管理や健康維持のために実践する人も増えています。
グルテンフリーの詳しい始め方についてはこちらの記事をご覧ください。
グルテンフリーに関連する疾患・症状

グルテンフリーがなぜ注目されるのか、その背景にはグルテンが関わる疾患や症状があります。
ご自身の体調と向き合うためにも、正しい知識を身につけましょう。
| 用語 | 解説 |
|---|---|
| セリアック病 | グルテンを摂取すると、免疫系が自身の小腸を攻撃してしまう自己免疫疾患です。腹痛、下痢、栄養吸収障害などを引き起こします。診断には医師による検査が必要です。 |
| 非セリアック・グルテン過敏症(グルテン不耐症) | セリアック病や小麦アレルギーではないものの、グルテンを摂取することで、倦怠感、頭痛、腹部の膨満感など、様々な不調が現れる状態を指します。 |
| 小麦アレルギー | 小麦に含まれるタンパク質を異物とみなし、免疫系が過剰に反応するアレルギー疾患です。蕁麻疹(じんましん)や呼吸困難など、即時型のアレルギー反応が特徴です。 |
| リーキーガット症候群 | 腸の粘膜に隙間ができ、未消化物や有害物質が血中に漏れ出してしまう状態のこと。グルテンがその一因となる可能性が指摘されています。 |
グルテンフリー食品に関する用語

グルテンフリー生活を支えるのは、小麦の代わりとなる様々な食材です。
代表的なものを知っておくと、商品選びや料理の幅が広がります。
代替粉
小麦粉の代わりに使用される、グルテンを含まない粉の総称です。
- 米粉: お米から作られる粉で、パンやお菓子、料理のとろみ付けなど幅広く使えます。もちもちとした食感が特徴です。
- 玄米粉: 玄米を粉にしたもので、白米の米粉よりもビタミンやミネラル、食物繊維が豊富です。
- 大豆粉: 大豆から作られ、高タンパクで低糖質なのが魅力です。独特の風味があります。
- そば粉: そばの実から作られますが、製品によっては小麦粉が混ぜられていることがあるため、「十割そば」など表記の確認が必要です。
ノングルテン
「グルテンを含まない」という意味で、グルテンフリーとほぼ同義で使われることが多い言葉です。
ただし、日本の食品表示基準には「グルテンフリー」の明確な基準値が定められていない点に注意が必要です。
グルテンフリー認証と注意点
安心してグルテンフリー製品を選ぶためには、認証マークや表示についての知識が役立ちます。
特に注意したい用語も確認しておきましょう。
グルテンフリー認証
第三者機関が、製品のグルテン含有量が一定基準値以下であることを証明するマークです。
国や地域によって基準は異なりますが、国際的な基準ではグルテン含有量が20ppm(0.002%)未満であることが一般的です。
- GFCO(The Gluten-Free Certification Organization): 米国の認証機関で、より厳しい基準(10ppm未満)を設けています。このマークがある製品は、厳格な管理下で製造されているため、信頼性が高いと言えます。
コンタミネーション(交差汚染)
「コンタミ」と略されることもあります。
食品の製造過程において、本来含まれていないはずのグルテンが意図せず混入してしまうことを指します。
例えば、小麦製品と同じ製造ラインでグルテンフリー製品を作る際に起こる可能性があります。
重篤な症状を持つ方は、コンタミネーションの可能性に関する注意書きまで確認することが重要です。
まとめ
今回は、グルテンフリーに関連する基本的な用語を解説しました。
用語の意味を正しく理解することは、ご自身の健康管理や安全な商品選びに直結します。
この用語集を参考に、より快適なグルテンフリーライフをお送りください。