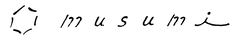出産祝いのお返し「内祝い」は必要?不要?相場や時期など基本のマナーを徹底解説
出産内祝いは本当に必要?「お返し」との違い

赤ちゃんのご誕生、おめでとうございます。
多くの方から祝福を受け、幸せを実感されていることと思います。
その一方で、「出産祝いのお返し、いわゆる『内祝い』って本当に必要なの?」と迷われている方もいらっしゃるかもしれません。
「内祝い」本来の意味とは
「内祝い(うちいわい)」という言葉は、本来「身内のお祝い」を意味します。
つまり、お返しとして贈るものではなく、「我が家におめでたいことがありました。
この喜びを分かち合ってください」という意味を込めて、親しい方々へ自発的に配ったものでした。
昔は、出産や結婚などの慶事があった際に、お赤飯や紅白のお餅などを配る風習がありました。
これが内祝いの原型です。
現代における「出産内祝い」の役割
現代では、内祝いの意味合いが少し変化しています。
特に出産においては、「出産祝いをいただいた方へのお返し」という意味合いが強くなっています。
もちろん、本来の意味も残っており、「赤ちゃんの誕生を報告し、お披露目する」という意味も込められています。
いただいたお祝いへの感謝の気持ちと、「これから親子ともどもよろしくお願いします」というご挨拶を兼ねて贈るのが、現在の一般的な「出産内祝い」と言えるでしょう。
お返しは不要?贈るべきケース・不要なケース
基本的には、出産祝いをいただいたら内祝いを贈るのがマナーとされています。
感謝の気持ちを形にして伝えることは、今後の良好な人間関係を築く上でも大切です。
- 贈るべきケース: 職場の上司、同僚、友人、親戚などからお祝いをいただいた場合。
-
不要、または検討が必要なケース:
- 「お返しは不要(いらない)」と明確に言われた場合: 相手のご厚意を汲み、無理に贈らない方が良い場合もあります。ただし、社交辞令の場合もあるため、関係性によります。後日、赤ちゃんの写真とともにお礼状を送るだけでも喜ばれます。
- 高額すぎるお祝いをいただいた場合: 特に両親や近しい親戚から高額なお祝い(ベビーカーやベビーベッド、高額な現金など)をいただいた場合、「赤ちゃんの生活のために使いなさい」という支援の意味が強いことがあります。この場合、相場通りの半返しにこだわらず、感謝の言葉を丁寧に伝え、後日食事に招待するなどで代えることもあります。
- 会社や団体名義でいただいた場合: 福利厚生の一環や「一同」からの場合、お返しが不要なケースもあります。職場の慣習を確認してみましょう。個別に返す必要がない場合は、休憩室で皆さんが食べられるようなお菓子を配るのも良い方法です。
【基本マナー】出産内祝いを贈る際に押さえるべきポイント
出産内祝いを贈る際には、相手に失礼がないよう、基本的なマナーを押さえておくことが重要です。
特に「時期」「相場」「のし」の3点は必ず確認しましょう。
贈る時期:いつまでに贈る?
出産内祝いを贈る時期は、生後1ヶ月頃(お宮参りの時期)が一般的です。
産後すぐはママの体調も不安定で、赤ちゃんのお世話も大変です。
出産祝いは生後7日~1ヶ月頃にいただくことが多いため、それらが落ち着いた生後1ヶ月~2ヶ月頃までに贈るのが目安となります。
もし贈るのが遅れてしまった場合でも、必ずお詫びの言葉とともに内祝いを贈りましょう。
金額の相場:いくらくらい?
出産内祝いの相場は、いただいたお祝いの金額の「半額(半返し)」から「3分の1」程度が目安です。
- 半返しが基本: 友人、同僚、目下の方など。
- 3分の1程度でも良い場合: 両親、親戚、上司など、目上の方から高額のお祝いをいただいた場合。相手の負担にならないよう、3分の1程度に抑えることもあります。
いただいた品の金額がわからない場合は、インターネットなどで大まかな価格を調べて目安にすると良いでしょう。
「のし(熨斗)」の選び方・書き方
出産内祝いには、必ず「のし紙」をかけて贈ります。
間違ったものを選ぶと失礼にあたるため、注意が必要です。
水引の種類
「紅白の蝶結び(花結び)」の水引を選びます。
蝶結びは「何度あっても良いお祝い事」に使われます。出産はまさしくこれにあたります。
(※結婚祝いなどに使われる「結び切り」は、「一度きりであってほしいこと」に使われるため、間違えないようにしましょう。)
表書き
水引の上段中央に「内祝」または「出産内祝」と書きます。
名入れ
水引の下段中央に、「赤ちゃんの名前」を書きます。
これは、赤ちゃんがいただいたお祝いへのお返しであり、「赤ちゃんの名前をお披露目する」という意味合いがあるためです。
読み方が難しい名前の場合は、ふりがなを振ると親切です。
メッセージカードは添えるべき?
必須ではありませんが、できるだけ添えることをおすすめします。
品物だけを送るよりも、お祝いへの感謝の気持ちや、赤ちゃんの名前の由来、現在の様子などを記したメッセージカードが添えられている方が、相手に温かい気持ちが伝わります。
【相手別】出産内祝いの相場目安

内祝いの相場は「半返し~3分の1」が基本ですが、相手との関係性によって柔軟に対応しましょう。
親・親戚へ
両親や祖父母からは、高額なお祝いや育児用品そのものをいただくケースも多いです。
今後のために使いなさい」という支援の意味合いも強いため、無理に半返しにする必要はありません。
相場の3分の1程度や、感謝の気持ちが伝わる品物で十分でしょう。
後日、赤ちゃんの顔を見せに帰省する際に、手土産を兼ねるのも良い方法です。
上司・目上の方へ
目上の方からいただいた場合も、半返しにこだわらず、3分の1程度でも失礼にはあたりません。
金額よりも、質の良いもの、相手の好みに合わせたものを選ぶ心遣いが大切です。
高額すぎるお返しは、かえって相手に気を遣わせてしまう可能性もあります。
友人・同僚へ
友人や同僚へは、基本的に「半返し」が目安です。
気を遣わせない、消えもの(お菓子やドリンク)や、実用的なタオルなどが喜ばれます。
連名でいただいた場合
職場の同僚などから「〇〇一同」として連名でお祝いをいただいた場合は、いただいた総額を人数で割り、その一人当たりの金額の「半返し~3分の1」程度の品物を個別に贈るのが丁寧です。
ただし、一人当たりの金額が少額になる場合は、全員で分けられる個包装のお菓子などを「皆様で」として贈るのでも構いません。
【早見表】相手別・いただいた金額別の相場目安
| いただいた金額 | 内祝いの目安 (半返し) | 内祝いの目安 (3分の1) | 主な相手 |
|---|---|---|---|
| 5,000円 | 2,500円 | 約1,700円 | 友人・同僚 |
| 10,000円 | 5,000円 | 約3,300円 | 友人・同僚・親戚 |
| 30,000円 | 15,000円 | 10,000円 | 親戚・上司 |
| 50,000円 | 25,000円 | 約17,000円 | 両親・親戚・上司 |
| 100,000円 | 50,000円 | 約33,000円 | 両親・祖父母 (支援の意味が強ければ、相場にこだわらなくても良い) |
※あくまで目安です。地域の慣習や相手との関係性に応じて調整してください。
出産内祝いに関するよくあるQ&A

Q. お祝いをいただいていない方にも贈るべき?
A. 基本的に贈る必要はありません。
内祝いの本来の意味(喜びのお裾分け)で贈ることも間違いではありませんが、現代ではお祝いをいただいていない方に贈ると、かえって相手に「お祝いを催促された」と受け取られかねません。
お祝いをいただいていない方へは、出産報告のハガキやSNSでの報告で十分でしょう。
Q. 「お返しはいらない」と言われたら?
A. 相手との関係性によります。
本心から気を遣って言ってくれている場合(特に両親や親しい親戚など)は、ご厚意に甘えても良いでしょう。
その場合も、感謝の言葉と赤ちゃんの写真は必ず送りましょう。
社交辞令の可能性もある場合(上司や取引先など)は、相手に負担にならない程度の、心ばかりの品を贈るのが無難な場合もあります。
Q. 贈るのが遅れてしまった場合は?
A. 気づいた時点ですぐに手配しましょう。
贈る際には、必ずメッセージカードやお礼状を添え、「ご挨拶が遅くなり申し訳ありません」というお詫びの言葉を一言書き添えるのがマナーです。
Q. 喪中の場合はどうする?
A. 相手または自分が喪中の場合、時期をずらします。
四十九日(忌明け)を過ぎてから贈るのが一般的です。
その際、のし紙はかけず、無地の奉書紙や白い短冊に「内祝」と記し、お悔やみの言葉とお祝いへの感謝を記した手紙を添えると、より丁寧です。
まとめ:感謝の気持ちを伝える出産内祝い

出産内祝いは、単なる「お返し」ではなく、赤ちゃんの誕生を祝福してくれた方々へ感謝を伝え、「これからよろしくお願いします」とご挨拶する大切な機会です。
「必要か不要か」で言えば、現代の日本では「贈るのがマナー」とされています。
しかし、一番大切なのは形式よりも「ありがとう」の気持ちです。
産後の忙しい時期ですが、相手の顔を思い浮かべながら、喜んでもらえる品を選んでみてはいかがでしょうか。